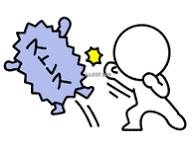子どもに学ぶ
40年前のこと、小学5・6年生を受け持ったクラスにAちゃんという女の子がいた。Aちゃんは学級開きの日に、「私のお母ちゃんは、私を生んだときに看護師さんに何て聞いたか、先生わかる?」と聞いてきた。私は「女の子ですか、男の子ですか?と、聞いたんとちがうかな」と返すと、「違うよ。お母ちゃんは、赤ちゃんは声を出して泣いていますか、と聞いたんやって。」
Aちゃんのお母さんとお父さんは聾唖者のご夫妻で、生まれてきた子どもは自分たちのように声が出ないのではないかと心配だったというのだ。
Aちゃんは、市立福祉センターで手話を習い、両親と何でも会話ができた。しかし、嫌なことが2つあったと話してくれた。買い物で電車に乗ったとき、大好きなお母さんに手話で話そうとすると「やめなさい」と遮られたことだ。「黙っていたら障害者だと気づかれないから・・・。」。それと、初めて友だちが家に遊びに来た時、「Aちゃんのお母さんは、牛のようやな。」「『もう、もう』と言うだけで、しゃべられへんの?」と言われたこと・・・。
学校では明るく元気なAちゃんだが、胸の奥深くに「障碍者の子ども」という重しがあることに胸が熱くなった。私にとって、この2年間はたくさんの学びの日々だった。Aちゃんは、担任の私と交換日記をしたいと言ってきた。そのノートは卒業の日まで毎日続いた。今思えば、交換日記は学校の様子を両親に伝える有効な一つの手段だった。