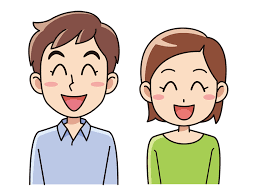生活を綴る
8+8+8=24。1日は24時間。子どもが学校で過ごすのは8時間。そこには「学習者」としての子どもがいる。一方、「おはようございます」までの8時間と「さようなら」のあとの8時間は家庭や地域で過ごす時間だ。ここには「生活者」としての子どもの姿がある。
教師は、学校の子どもを見ているだけでは子どもを理解したことにはならない。より深く子どもを理解するには、家庭や地域の様子を知ることだ。それには、「子どもの生活事実を綴る」ことが大切である。
子どもの暮らしをありのままに綴ることで、驚き・発見・喜び・悲しみ・葛藤などキラキラした心の動きが見えてくる。暮らしの事実から出てくる言葉や表情、とりわけ心に深く残った出来事を紡ぐことができる。例えば、お母さんの帰りを夜遅くまで待っている子どもの気持ちを「寂しい気持ちで待っている」と書くのではなく、その時の様子を「タンスのお母さんの服の匂いを嗅いでいる」と、「事実」を綴ることで子どもの心情が伝わってくる。
ところで、「いい文章」とはどのような文だろうか。一言で言えば「わかりやすい文」である。では、「わかりやすい文」とはどういうものか。
第1に、実際に体験や経験したことなど「事実」(ほんとうにあったこと)が書かれている文章である。
第2に、その事実を「ありのまま」に綴っている文である。「ありのまま」というのは、単に時間の経過と共に綴ることではない。ふだんの生活の中で、うれしかったことや悲しかったこと、驚いたり発見したことなど、時々に思ったり感じたことを概念的な言葉でなく、素直に「ありのまま」に言葉にすることである。「うれしい」「楽しい」や「悲しい」「辛い」という言葉でなく、その時々のそうした気持ちを「事実」に即して綴るのだ。
第3は、その文に共感や好感・親近感を持ってくれる読み手(仲間)がいることだ。「わたしみたいに思っている人が、他にもいると思って書きました。」という安心感や信頼感がのびのびした文を生み出す。 日常生活の「ちょっと・すこし・わずか・かすか・ほのか・ささやか・こまやか・ひめやか」というようなことをありのままに綴るのである。